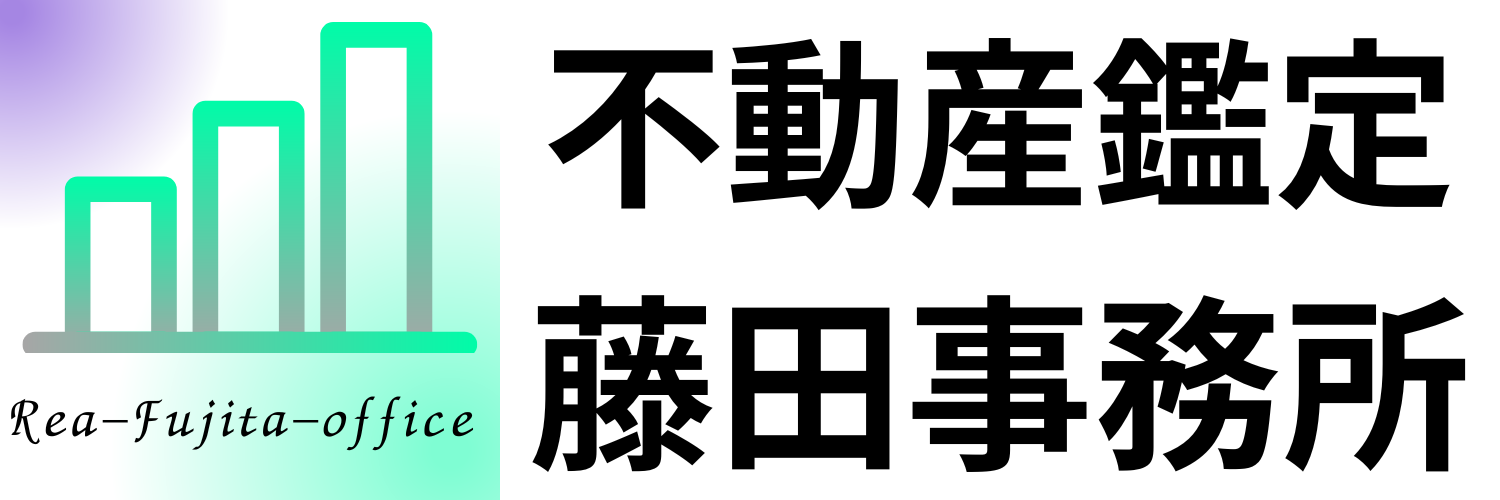「クララとお日さま」 カズオ・イシグロ
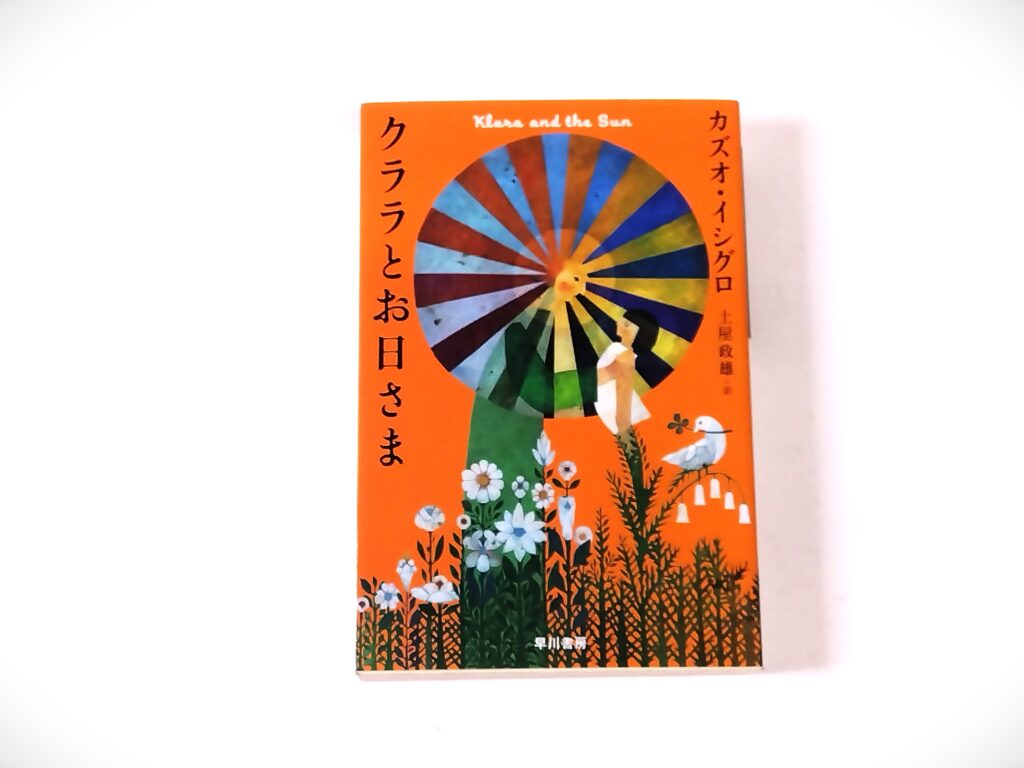
カズオ・イシグロのノーベル賞受賞後第1作。ノーベル賞を受賞した後に新たな作品を出すというのはすごいプレッシャーなのではなかろうか。世界中の共通認識として最高であると認められた作家というブランドを身につけたところで、さらに新作を出す。どう考えても駄作は許されそうにない。その状況の中でさっそうと出てきた「クララとお日さま」。期待を完全に上回る出来のものでした。
カズオ・イシグロの小説を特徴づけているのは「信頼できない語り手」と呼ばれるテクニック。これは、小説の語り手の発言等は必ずしも信用できず、このミスリードを巧みに利用するテクニックです。このテクニックが典型的に活用されているのは「日の名残り」(今から30年近く昔の小説)だろうと考えています。執事である主人公がちょっとスカした感じの発言の多かった過去を振り返る旅に出る。その中でスカしていた自分に気づく(気づくというより白状かもしれません、あるいは後悔・懺悔)。「信頼できない語り手」の作法が十分に活用された作風でした。
一方「わたしを離さないで」(こちらは今から20年ほど前の小説)という小説がありまして、こちらは「信頼できない語り手」というより「怪しい舞台設定」。どうも怪しげな舞台設定が、きちんと説明されることなく小出しに出て来て、結局最後まで説明がない。ただ異常な舞台設定だけに、その分感情が際立つ効果がありそうである。
「クララとお日さま」は「わたしを離さないで」に近い。クララはAF(人工親友のことだそうです)だと表紙の解説にいきなり書いてあります。人工親友ってなんだ。開始前から怪しい。その後怪しい設定が次々に放り込まれてきますが、最後までちゃんとした説明はない。でも私は「なぜこんな設定をしなければならなかったのか」という自問を頼りに読み進めていくのです。つまり、AFなどという新概念を持ち出さずとも、人間の「親友」でよいはずですが、わざわざAFなんて概念を持ち込むには理由があるはずで、それはこの舞台設定により人間の感情などが際立つとカズオ・イシグロが考えたからに違いないからです。よくミステリー小説の原則として「拳銃が出てきたら誰かが殺されなければならない」というものがあるそうです。そりゃそうですね、散々拳銃が登場したあげく、誰も殺されなかったミステリー小説は存在理由がなかろう。ですので怪しい舞台設定の投入は、そうすべきとカズオ・イシグロ考えた理由がある訳で、この点について妄想する自由をカズオ・イシグロは与えてくださっているわけですね、どんどん妄想しちゃってくださいって。つまり本作は言うなれば、偉大なるカズオ・イシグロが妄想マニアにささげる一冊。
ラストでクララの前から去る店長の歩き方、アレっと思ったのですが、解説で鴻巣友季子さんがこの歩き方について「イシグロの寡黙な筆致の白眉がここにある。21世紀に必読の名著」と少々大げさなことを書いているので、きっとこれは間違いなくドストエフスキーさん及びトルストイさんも使った例のヤツに違いない。でも私のようなものがエラそうにここで書きなぐるのは違うと思うのでこれくらいにしておきます。ところで鴻巣さんというと、僕としては「風と共に去りぬ」又は「緋色の記憶」(こちらは知名度が低いかな)の翻訳。でも翻訳家以外に文芸評論家でもあったのですね。初めて知りました。
ところでこの本、文庫なのに1,500円もする。最近文庫の値上がりがちょっと凄いな、と思っていたけれど〇〇文庫はちょっと激しすぎないだろうか?ほかのレーベルより微妙に大きくていつも使っている文庫カバーに入らないから不便だし。良い小説が多いから強気なのだろうか。