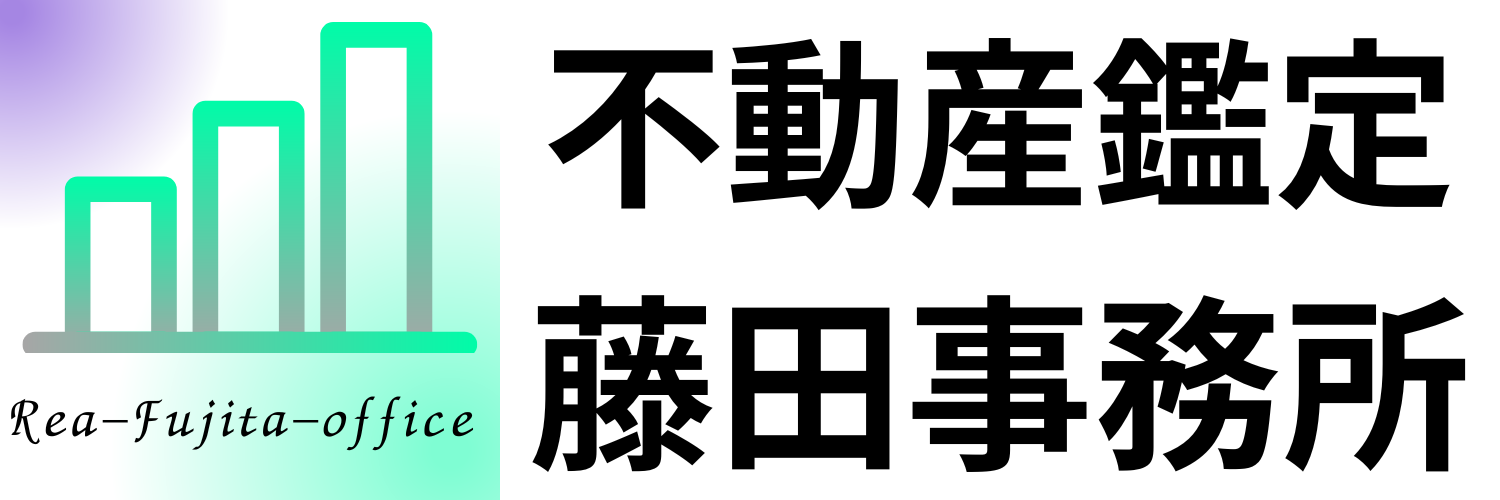「鑑定評価書のご説明⑪」「Ⅸ.鑑定評価額の決定の理由の要旨 〔Ⅰ〕価格形成要因の分析 2.地域分析_2」

今回は「鑑定評価書のご説明⑪」として「Ⅸ.鑑定評価額の決定の理由の要旨 〔Ⅰ〕価格形成要因の分析 2.地域分析_2」です。
「地域分析」が前回で終わらなかったのでその続きです。
【記載例】
(3)近隣地域の状況
対象不動産の所在する近隣地域の地価形成に影響をもつ地域要因の主なものは、下記のとおりである。
①近隣地域の範囲
対象不動産の前面街路(〇〇市道123号線)沿いで、対象不動産を中心として東方へ約50m、西方へ約50mの範囲の地域
②地域の特性等
a.街路の状態
接面道路は南側の幅員約6.0mの舗装市道(〇〇1234号線)が標準である。街区はほぼ整然としており、系統・連続性は普通である。
b.交通・接近条件
JR〇〇線「〇〇」駅から近隣地域の中心まで南方へ道路距離約1.2㎞に位置する。
その他の施設との接近性は次のとおり。
〇〇市役所 :道路距離約450m
スーパー〇〇店 :道路距離約700m
〇〇小学校 :道路距離約180m
〇〇バス〇◇停留所 :道路距離約350m
c.環境条件
地勢はほぼ平坦であり、供給処理施設としては、上下水道、都市ガスがある。危険嫌悪施設等は特にない。
d.行政的条件
市街化区域、第2種住居地域、指定建蔽率60%、指定容積率200%、基準容積率は指定容積率と同じである。
e.その他の条件
特にない
③ 将来動向等
当面は現状を継続すると予測する。
④ 標準的画地及び標準的使用
a.標準的画地
間口:15m
奥行:20m
規模:300㎡
形状:長方形地
接面道路との関係:幅員約6.0mの舗装市道に南向きに接道する中間画地で近隣地域のほぼ中央に所在する。
b.標準的使用
戸建住宅の敷地
~~~~~~~~~~~~~~~~記載例ここまで~~~~~~~~~~~~~~~
【ご説明】
「2.地域分析_1」では、市区町村という行政的な区分で「地域」を抽出してその特徴を記載しており、今回はそれよりも小さな区分である近隣地域についての特性を記述している。
近隣地域とは「対象不動産の属する用途的地域であって、より大きな規模と内容とを持つ地域である都市あるいは農村等の内部にあって、居住、商業活動、工業生産活動等人の生活と活動とに関して、ある特定の用途に供されることを中心として地域的にまとまりを示している地域をいい、対象不動産の価格の形成に関して直接に影響を与えるような特性を持つものである。」と不動弾鑑定基準は定義しています。つまり鑑定評価の対象となる不動産の周辺で、用途によってまとまっている地域ということです。
通常の不動産鑑定では①近隣地域の標準的画地の標準価格(一般に「地域の価格相場」と言われている価格水準のことです。)を求め②その標準価格に、対象不動産の個別性(角地であるとか南向きであるとか、価格に影響を与える個々の不動産の特性のことです。)を考慮して鑑定評価の対象となる不動産の価格を求めていきます。
したがって①のためにその地域の価格水準に影響を及ぼすと考えられる要因についての調査結果をここに記載していきます。
街路の良しあし、利便施設からの距離、インフラの整備状況等などです。
そしてそれらの調査結果に基づいて「④ 標準的画地及び標準的使用」を不動産鑑定士が判断し記載します。
標準的画地及び標準的使用とは、その近隣地域で最も標準的な画地及びその画地の利用形態のことをいい、一般的に「この地域の土地の相場は〇〇円である。」と言った場合にはその相場はこれらの標準的画地及び標準的使用を前提としていると考えられます。
以上