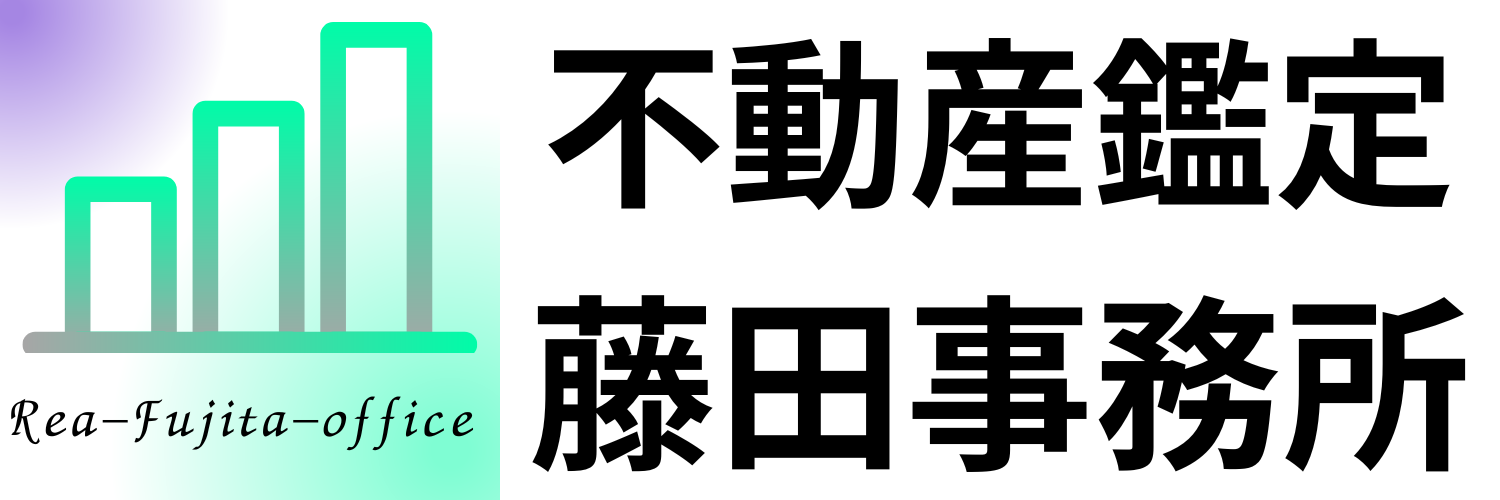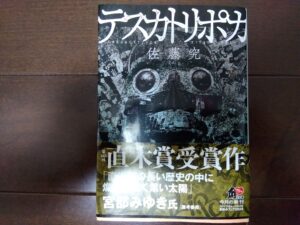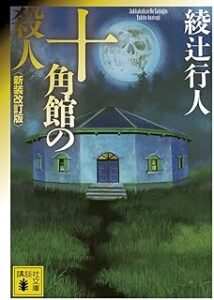「鑑定評価書のご説明⑫」「Ⅸ.鑑定評価額決定の理由の要旨〔Ⅰ〕価格形成要因の分析 3.個別分析」

今回は「鑑定評価書のご説明⑫」として「Ⅸ.鑑定評価額の決定の理由の要旨 〔Ⅰ〕価格形成要因の分析 3.個別分析」です。
前回及び前々回の「地域分析」で対象不動産が所在している地域を分析し、今回の個別分析では対象不動産そのものを分析します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 記載例 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3.個別分析
(1) 対象不動産の状況
① 近隣地域における位置
近隣地域のほぼ中央部に位置する。
② 土地の状況
対象不動産は、駐車場の敷地として利用されている。
a.街路条件
北西側で幅員約10mの舗装区道第○号線(○○通り)に接面する。道路の種類は、建築基準法第42条第1項第1号の規定に該当する道路であり、近隣地域の標準的画地と同じ。
b.交通・接近条件
○○線X駅に徒歩○分、地下鉄○○○線Y駅に徒歩○分であり、近隣地域の標準的画地と同じ。
c.環境条件
地域の特性から判断して、標準的である。
d.行政的条件
近隣地域の標準的画地と同じ。
e.画地条件
間口約26m、奥行約21~27m、地積は605.75㎡のほぼ台形地である。
道路面とほぼ等高に接面し、画地内に高低差はない。
③ 埋蔵文化財の有無及びその状態
○○市教育委員会に聴取したところ、対象不動産は周知の埋蔵文化財包蔵地には含まれていないとのことであった。
以上により、対象不動産は埋蔵文化財が価格形成に大きな影響を与えることがないと判断されるので、価格形成要因からは除外して鑑定評価を行う。
④ 土壌汚染の有無及びその状態
土地の閉鎖登記簿で過去の土地所有者名を調査した。対象不動産は平成〇年以降駐車場の敷地として利用されており、昭和41年と昭和55年の住宅地図からは、対象不動産は戸建住宅の敷地であった。地元精通者への聴取により、戦前も住宅地であったが、それより以前は畑であった可能性がある。隣接地及び周辺において土壌汚染を懸念する施設はない。
また、土壌汚染対策法をはじめとした法令による土壌汚染状況調査を行う義務はなく、調査の実施も命じられていない。
なお、同法の規定による要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定されている土地は含まれておらず、過去においてこれらの指定又は改正前の同法の規定による指定区域の指定の解除がなされた履歴もない。
以上により、対象不動産は有害物質の使用の形跡は認められず、土壌汚染が存在することを示す端緒は発見されなかった。土壌汚染が対象不動産の価格形成に大きな影響を与えることはないと判断されるので、土壌汚染を価格形成要因から除外して鑑定評価を行う。
⑤ その他(地下埋設物、越境物等)
現地調査において隣接地からの越境物は認められず、地下埋設物についても外観からは基礎杭の頭やコンクリート基礎の露頭部分などは一切認められなかった。地歴調査については、○年の住宅地図から対象不動産は戸建住宅の敷地として使用されていたと推定されるので、対象不動産の地中にかつて大規模建築物を支えていたコンクリート基礎等が残存する可能性は低い。
また、対象不動産に関して地盤及び地質の調査は行われておらず、都庁備付けの地質地盤図を閲覧したが詳細は不明であった。しかし、隣接地及び周辺に4~5階建ての建物が存すること並びに案内者及び地元精通者への聴聞からは、特に利用の制約となる事項の存在は確認できなかった。
以上により、標準的な建築費での建築が可能なものと判断した。
⑥ 標準的画地と比較した増減価要因
~省略~
(2) 対象不動産の市場分析
① 対象不動産に係る典型的な需要者層
市場参加者として最も想定されるのは、対象不動産を取得の上、賃貸用不動産を建築し、運用して収益獲得を目指す投資家等と考えられる。
② 代替・競争関係にある不動産との比較における優劣及び競争力の程度
~省略~
以上から、代替・競争関係にある不動産と比べた対象不動産の優劣及び競争力の程度は、やや優れるものと判定した。
(3) 最有効使用の判定
立地条件及び形状・規模・日影規制による形態規制等の個別性等を勘案した結果、対象不動産の最有効使用は、標準的使用と同じ中層共同住宅地と判定した。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 記載例はここまで ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【ご説明】
個別分析は鑑定評価の対象となる不動産そのものの分析を行うことである。不動産鑑定評価基準では「不動産の価格は、その不動産の最有効使用を前提として把握される価格を標準として形成されるものであるから、不動産の鑑定評価に当たっては、対象不動産の最有効使用を把握する必要がある。個別分析とは、対象不動産の個別的要因が対象不動産の利用形態と価格形成についてどのような影響力を持っているかを分析してその最有効使用を判定することをいう。」となっています。
つまり、不動産の価格は「最有効使用を前提として把握される価格を標準」として形成されるということになっており、そのため不動産の価格を把握するために、その前提となっている最有効使用を把握する必要があり、その過程が個別分析である、ということです。
なんとも持って回ったややこしい事ですが、「不動産の価格をきちんと把握するためには、最有効使用を把握することが必要であるので、個別分析を通じて最有効使用をきちんと把握しなさい。」ということです。そのために「位置、街路及び交通・接近性の状態、環境、行政」などの状態を把握するとともに「埋蔵文化財、土壌汚染、地下埋設物等」についてもきちんと把握します。
そのうえで不動産の市場について把握し、これらの情報を踏まえたうえで対象不動産の最有効使用を判定するわけです。
ところで、最有効使用について少々触れます。
不動産鑑定評価基準の最有効使用の原則を抜粋します。
「不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用(以下「最有効使用」という。)を前提とした価格を標準として形成される。この場合の最有効使用とは、現実の社会経済情勢の下で客観的にみて、良識と通常の使用能力を持つ人による合理的かつ合法的な最高最善の使用方法に基づくものである。
なお、ある不動産についての現実の使用方法は、必ずしも最有効使用に基づいているものではなく、不合理な又は個人的な事情による使用方法のために、当該不動産が十分な効用を発揮していない場合があることに留意すべきである。」
これも少々持って回った文章ですが、競争原理によって価格が決まる場合には最も高価格を提示した人が落札するわけですが、この高価格を提示できるのは「最有効使用」をイメージできている人である。ということが背景にある訳です。
以上