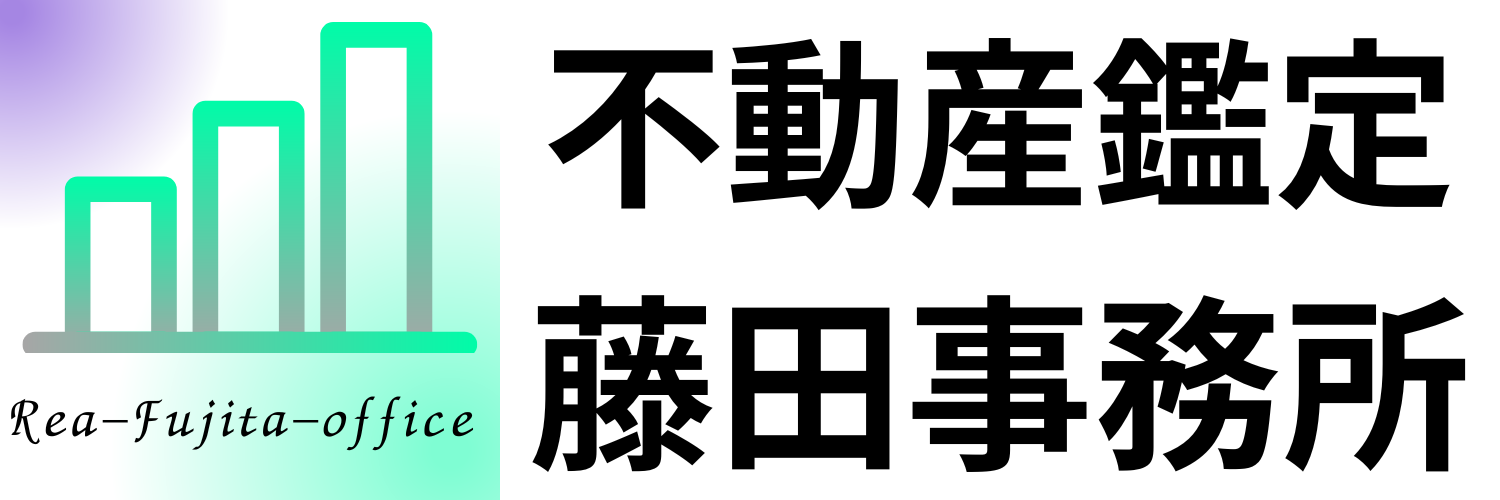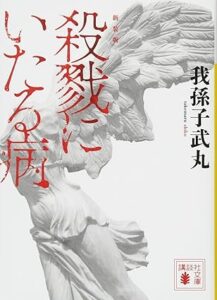わかったつもり (西林 克彦)
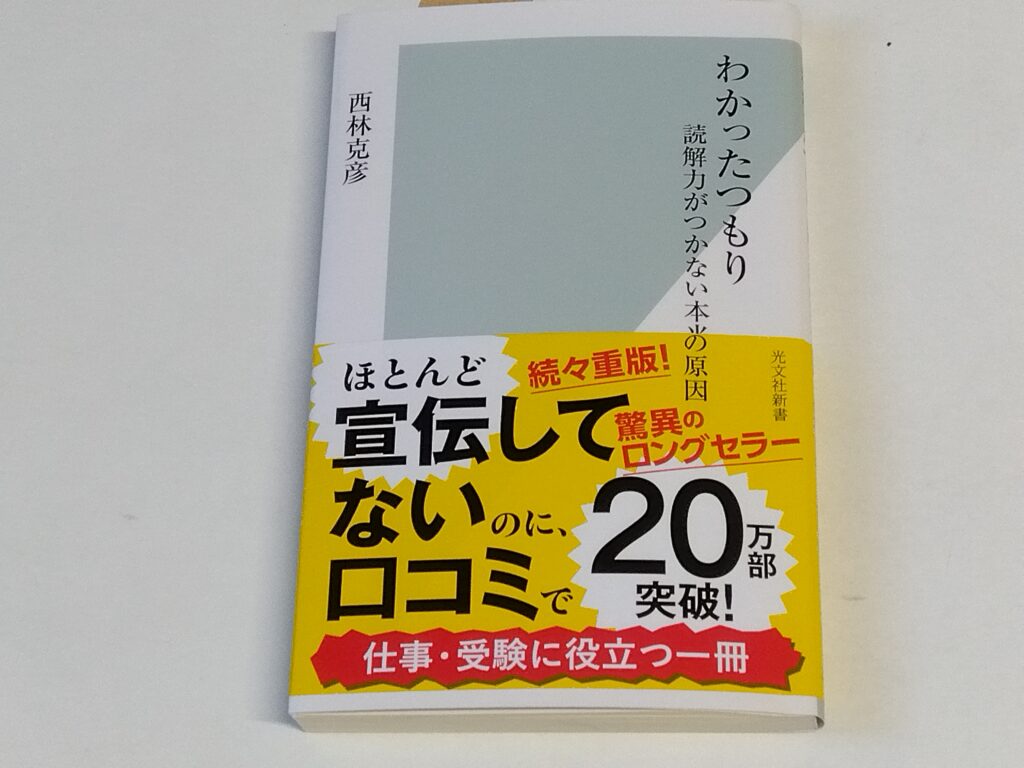
カバーの見返しのところに本文からの引用があります。ここがこの本の本質だと思うので引用します。
後から考えて不十分だというわかり方を「わかったつもり」とこれから呼ぶことにします。この「わかったつもり」の状態は、ひとつの「わかった」状態ですから、「わからない部分が見つからない」という意味で安定しているのです。わからない場合には、すぐ探索にかかるのでしょうが、」「わからない部分が見つからない」ので、その先を探索しようとしない場合がほとんどです。
「わかる」から「よりわかる」に至る過程における「読む」という行為の主たる障害は、「わかったつもり」です。「わかったつもり」が、そこから先の探索活動を妨害するからです。(以上「わかったつもり」のカバー見返しから引用)
先に取り上げた「十角館の殺人」「殺戮に至る病」の2作品については、2回目の読了までは「わかったつもり」が継続していたことになります。(ただし2回目の読了後に「わかったつもり」を卒業できた保証はない)
実際、これらの小説を読む場合には「なるべく騙されないで、一発で正答にたどり着けるように読みたい。」という意欲を持ち途中で事実関係を整理してメモったりしながら読むので、その時点では「今回はきちんと読めているな!」と(誤解しながら)読み進めているのですが、成功した試しはないのです。
この本では様々な例題で「わかったつもり」の類型及びそれらの乗り越え方が示されます。はじめは「小学校2年生の国語の教科書」から引用された「お母さん猫がもらわれていった子猫と電話で話す」というお話。さすがに一読後は「わからないところはないんじゃない!?」という感じなのですが、それなりに分析するとまだまだ全然読み込めていなかった、ということをわからせられます。こういった例題による提示が続き、最後には室生犀星の「ふるさとは遠きにありて思ふもの・・・」(小景異情)が例題に使われており、これについては答えがきっちりとは提示されていない。それでもなんとなく自分なりに考えてみる。こういった過程で当初の「カバー見返しの引用」の「わかったつもり」の乗り越える力を得る助けをいただく。そういう本です。
すべての読書は、ここに書いてある努力のためにするものだ。そう言っても決してオーバーではなかろうと思う。