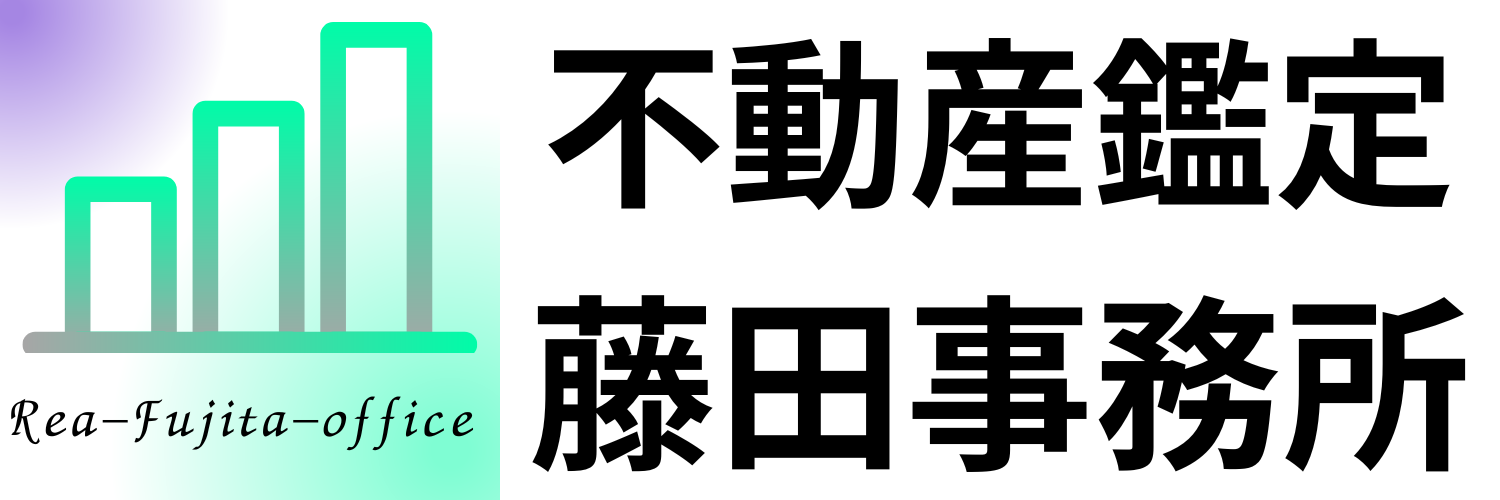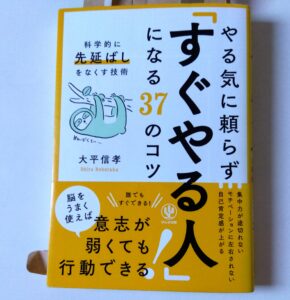加賀野八幡神社井戸(大垣市)

大垣市周辺は長良川・揖斐川など水量が豊富な河川により土砂が堆積した土地(扇状地)として形成されたことから地下水が豊富で、市内の各地に自噴の井戸がみられます。これらの井戸の中で「平水の名水百選」という水質が良いということで環境省が全国で100か所を選定したものに選ばれているのがこの「加賀野八幡神社井戸」です。つまり数ある大垣市内の井戸の中で最も水質が良かろうと思われる井戸です。
国道21号の加賀野の交差点を西方に進むと、間もなく鎮守の森然としたところが見えてきます。ここが加賀野八幡神社井戸。
神社の鳥居のわきに3つの石碑が並んでいます。それぞれ「加賀野八幡人社井戸」「後藤祐乗誕生の地」「加賀野城跡」と記されています。
後藤祐乗という方は室町時代の方で、刀剣の装飾つまり日本刀の各構成部分つまりつば、さや、つかなどといった装飾を施す職人の創始者だそうで、この方のご子孫が代々江戸時代末期にわたるまで刀剣の装飾職人として活躍されたということのようです。
その後藤祐乗さんの一族は室町時代ごろから、当地区を治めておりその居城が加賀野城だということです。この加賀野城は室町時代には攻め滅ぼされたようで、現地に遺構などは見当たりません。

一礼し敬虔な気持ちで鳥居をくぐると、すぐに井戸が見えてまいります。聞くところによればこの井戸はかなりの人気で、休日などは水を汲みに来る方々が列をなしておられるそうですが、私の訪れた日は少々雨模様(といいますか時々相当強い雨)の一日で、わざわざ水を汲みに来る方はおられませんでした。せっかくですので、少しだけ飲みます。
井戸の奥には八幡様のお社。せっかくですので敬虔な気持ちでお参りさせていただきました。