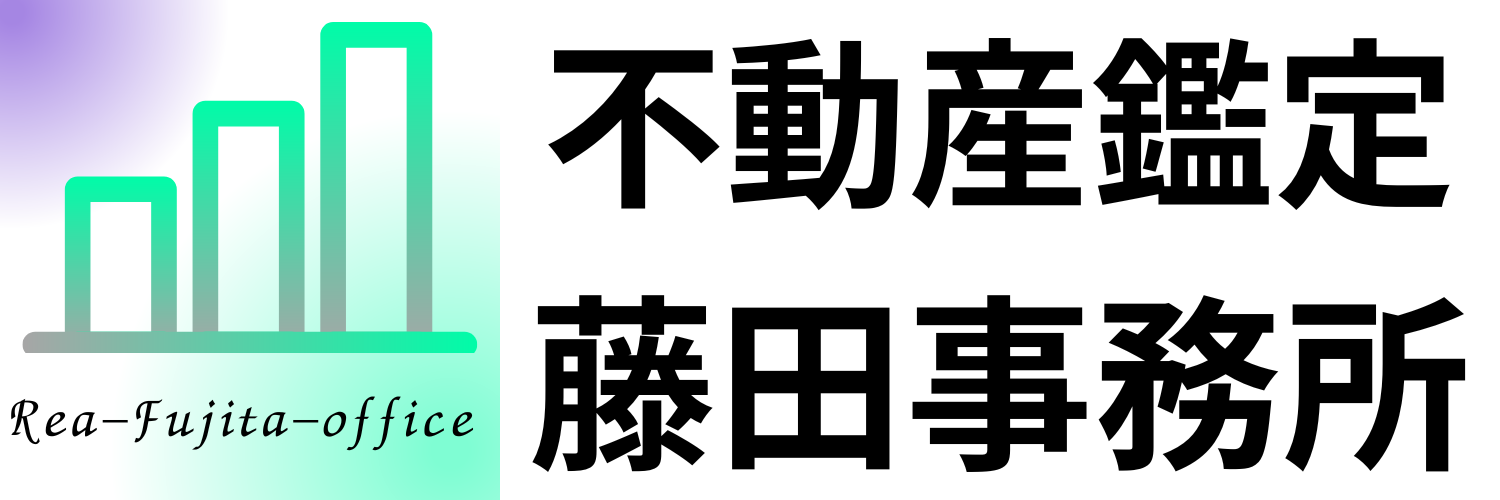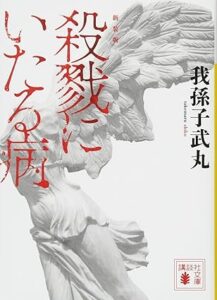十角館の殺人(綾辻 行人)
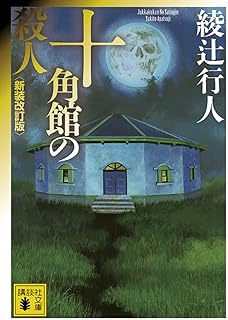
私の習慣で本は必ず2回以上読むことにしています。主な理由は、1回では大事なところを読み落としている可能性が高い、つまり1回目はストーリー展開に気を取られて読み飛ばすことが多いので、2回目だとそういったことから割と自由になれるので、拾えなかったものが拾える、ということです。これが、例えば「ドストエフスキー」や「夏目漱石」になると、名前負けの部分も否定できないのですが、2回でも少々自信がない。結局5・6回読み、何年かしてからまた読む。ということをしてしまう。結局自分の読解力が信用できていないということなのでしょう。
ところで、そのようなことではなく、なにしろ2回目を読まずにはいられない!というパターンがある。それがこの「十角館の殺人」つまりよくできたミステリー小説ではよくあることです。
ミステリ-小説ですので典型的には①何らかの事件が起こる②その間の経緯等で読者は犯人を想像しながら読み進める③犯人が明らかになる。というような①~③の流れをたどるのですが、③の犯人があまりに意外なものだと「自分の読んでいたのは何だったんだ?」という気持ちが強く働き、「2回目を読まずにはいられない。」ということになる訳です。
結果として、2回目を読むことによって、作者の目論見通りに先入観で判断をしていて、あっさり読み間違いをしていることに気づくということが待っているわけです。
「十角館の殺人」は、連絡の取れない無人島に大学サークルの仲間が集まり事件が進行し、一方本土側でもそのサークルの縁故者らが平行して動くということで進んでいきます。
ジャンルとしては「新本格」といいますか調べてみるとこのジャンルの第1作ということのようです。
もともと日本の推理小説は横溝正史、松本清張らに代表されるある程度の社会性を背景にした推理小説が有力だったわけですが、この社会性をある程度排除して、純粋にミステリーな部分に特化していこうとするものが「新本格」と呼ばれるジャンルだそうです。
ボソッと一言つぶやき、という感じで犯人が明かされる。それも「私が犯人です」ということではなく、そのつぶやきが「それだったら犯人は〇〇なの!?」ということになります。(ぼんやり読んでいるとこれにも気づかない恐れがありますから、1回目からある程度集中して読んでください。)かなりの頭の体操になります。推理小説好き必読。
この小説が映画化されたそうですが、いったいどうやって犯人を描いたのか!?
以上