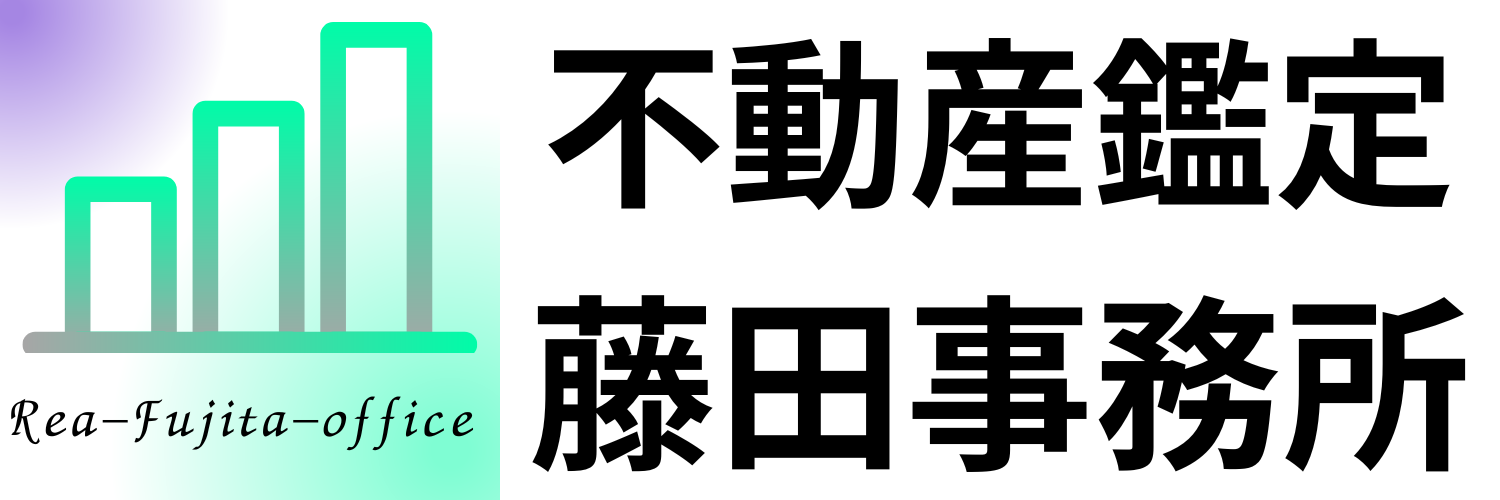墨俣一夜城(大垣市墨俣町)

「墨俣一夜城」このワードには、豊臣秀吉(当時は木下藤吉郎)が織田信長の命に従って一夜で築き上げた城という意味が含まれていると考えられます。司馬遼太郎の「国盗り物語」では一夜でとは書かれていませんが、それでも織田信長が藤吉郎の才覚・行動力を認めて信頼を得ることとなり、天下人となっていくストーリーの初期における重要なエピソードとされています。しかし、「一夜」は無理だということはわかりますが、さらに「城」であることも疑わしい。といいますか、「国盗り物語」においても「城」ということにはなっておらず砦ないしは柵であったと考えるのが妥当である。とは言っても、攻め込もうとしていた美濃の守りは強く、砦ないし柵を作ったことであっても大変なことである。

しかし、どうも話はこれでおさまらないようです。さすがに城は無理としても砦ないし柵であっても疑わしいらしい。つまり、墨俣一夜城のエピソードを根拠づけるエビデンスはほとんどが江戸時代の「軍記物」的な文書であるため信憑性が低く、信頼性の高い文書でこの「墨俣一夜城」のエピソードを確認しうるものは存在しないらしい。
あまり掘り下げると、反撃をくらう可能性がありますのでこのあたりにしておきます。織田信長が美濃の国を攻めあぐねていたところで、木下藤吉郎が大きな力となり、美濃の国に攻め込むにあたってはこの墨俣周辺から攻め入ったような事実はあったようです。それに、その藤吉郎の立身出世物語は間違いない事実である訳でそこに花を添える墨俣のエピソードなわけです。

そんな墨俣一夜城は現在では鉄筋コンクリート造5階建の威風堂々とした建物で、最上階の5階からは四方が展望できます。よく目をこらすと名古屋駅と思しき建築物も見えます。織田信長・豊臣秀吉はこの景色を眺めることはなかったのでしょうが、これから出世していく希望にあふれた心持ちでこのあたりを駆け巡ったのでしょう。