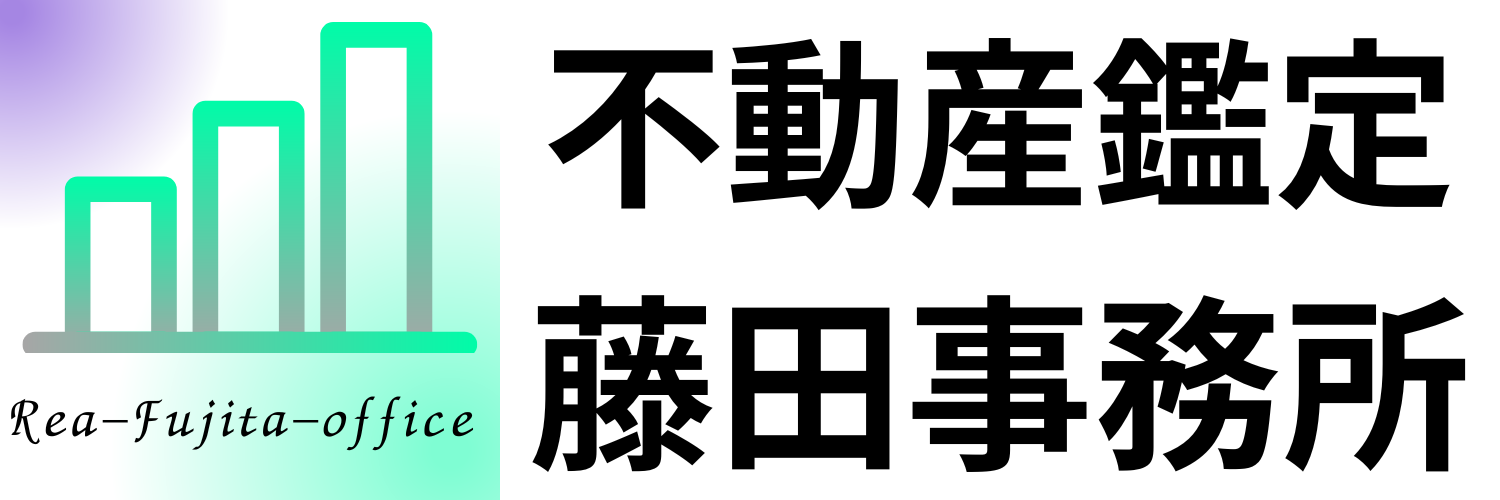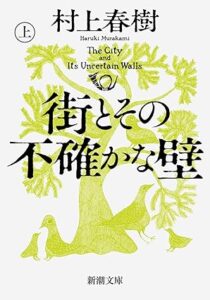日経新聞(10/28~11/19)
10/28日経 一目均衡:太平洋工業のMBOが買付価格2050=>2919に変更した。はじめから2919円だったらMBOを決めましたか、と聞いてみたい。ほとんどのMBOは「改革を実行すると短期的な利益水準が下がり株主に迷惑がかかる」という理由を挙げるが、そのような改革を上場したまま進めている企業は数多くある。トヨタ自動車の豊田章男社長のように「意志ある踊り場」と表現しビジョンを明確に表現した。MBOを口うるさいアクティビストや社外取締役から解放されていという思いで決しているのではなかろうか。
意見:最後の一節が核心だろう。深い考えのない経営陣とともに、顧問の監査法人、コンサルタントの資質も問題である。
11/17 日経 経済教室:供給力を高めるには ㊤資本蓄積重視への転換図れ:多くの人にとって現在最も関心のある経済課題は物価上昇の抑制だろう。これには経済学上2方法がある。一つは総需要の抑制、もう一つは総供給を増やすことである。これまでは一つ目が想定されてきた。しかし様々な背景から二つ目の方法、つまり「経営者は知恵を絞り、知恵を出し、知恵を利用して」将来にウエートを置いた意思決定への転換を期待する。
11/18 日経 経済教室:供給力を高めるには ㊥自動化と人材育成の両立を:現在人手不足が問題となっており、今後の人口減少が進むことから労働生産性向上が不可欠。ロボット・AIの活用が有効であるが、若手の訓練機会が縮小しうる。適切な処置とワークエンゲージメント向上の施策が欠かせない。
11/19 日経 経済教室:供給力を高めるには ㊦長期投資へ対話を深めよ:日本経済を巡る環境が大きく変化している。デフレ経済から脱却の兆しが表れ、持続的成長に向けた課題も出てきた。持続的な長期投資を通じた供給力向上のため、コスト圧縮、投資抑制の経営モデルからの脱却が喫緊の課題である。長期投資が進展し、供給力向上を通じた持続的成長を望みたい。
【供給力を高めるには について】
3日にわたって日経の経済教室で「供給力を高めるには」が論じられました。僕としては㊤が直感的にわかりやすく㊥㊦は少しついていき難かった。もともと「物価高対策」と言っても、「対策すべき程じゃないのではなかろうか?」と思うのですが、(政府が対策しようとしているのは僕の考えている事とは違うんでしょう、きっと)そうは言っても予定していた2%のインフレ率を少々超えている時もあるようだから、対策することも意義があるかもしれない。
そうすると、マクロ経済学の授業みたいな議論で言うと「総供給曲線の右方シフト」を目指せば「物価水準(P)は下方へ、国民所得(Y)は上方へ」という望ましい方向への変化が期待できるわけですが、「総供給曲線の右方シフト」はそんなに簡単ではなかろうが、そんな中でも㊤はそこに整合的だと思われます。
ただし、「総供給曲線の右方シフト」による経済問題の解決は「サプライサイダー」と言われる学派(?)の意見で、これはレーガン大統領の時に失敗した感じで、アメリカのクルーグマン教授は著書の中で「サプライサイド屋」と揶揄することがあって、どうも正面から大々的に主張しずらいのだろう、と感じます。日本では主張する人はいないし、逆にケインジアン的な「積極財政」の方が声が大きいですね。でもケインジアン流だとインフレ経済問題は解決しないのではなかろうか。
たぶんあの頃(レーガン時代)は時代背景とか、さらに「サプライサイダー」の方たちは「供給」に夢を持ちすぎ感があって「供給が需要を創造」というセイの法則に引っ張られすぎ感があってうまくいかなかったんじゃなかったかな。つまり供給を強化すれば需要はついてくる、と言っていて、そのココロは価格調整なのですが、タダでもいらない物はある訳ですし。無暗な供給強化は無駄でしょう。
そうじゃなくてキチンと需要のあるもので供給強化できて(ココがなかなか困難なんでしょうが。でも商売とか事業ってそれを実現しようとしてみんなで頑張ってるものでしょ。)労働分配も格好つけられれば、総供給曲線シフトによる望ましい状態に行けるんじゃないかと。
少し生意気かな?
以上