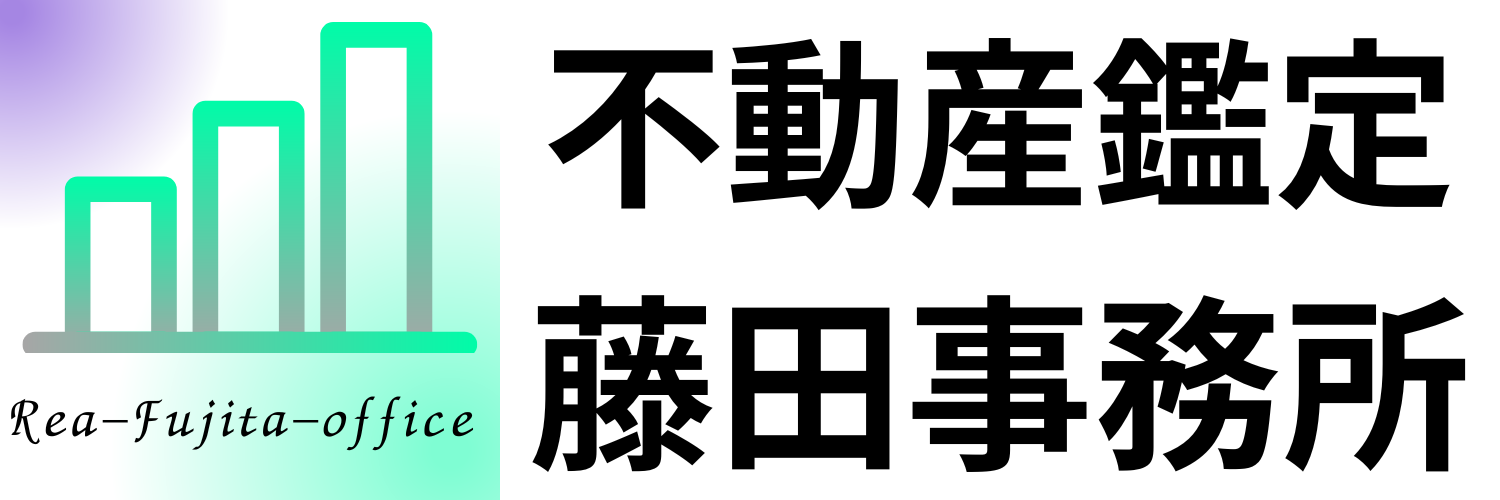日経新聞(11/10~11/21)
11/10~11/21
日経:やさしい経済学 『金融政策を検証する』日銀の「多角的レビュー」を踏まえ①自然利子率の低下②フォワードガイダンス③財政政策との関係、を解説している。①自然利子率は「景気を過熱も停滞もさせない中立的金利水準」をいう。ただし自然利子率は直接観測することはできず、経済モデルを用いた推計に依存する。この推計の不確実性が金融実務を難しくしている。日本では経済要因により潜在成長率が低下し、ひいては自然利子率が低下した。②自然利子率がゼロ近傍の実行下限に達したため、コントロールの余地が限られてしまい、「フォワードガイダンス」などの非伝統的な金融政策が必要になった。この場合「動学的不整合性」の問題が生じた。つまり将来についての約束をしても、その時点になると約束を守る動機を失ってしまう。日銀はインフレ率について「オーバーシュート政策」をとったが、これは目標達成後は有害となり得るためここに「動学的不整合性」が生じ得る。③日本では最近CPIで見たインフレ率は2%を超える水準が続いている。「物価水準の財政理論」では政府の財政支出が将来の増税で裏付けられていない場合、物価が上昇する可能性があるとされている。日本では「リカードの中立命題」がおおむね成り立っており、その結果として財政規律は保たれていると考えられる。デフレへの逆戻り、過度なインフレいずれも避けバランスを保つことが「通貨の番人」である中央銀行の使命である。
【藤田意見】
アベノミクス以降の金融及び財政政策についてきちんと論証されていた。ただし『「リカードの中立命題」がおおむね成り立っており、その結果として財政規律は保たれていると考えられる。』となっているが、『「リカードの中立命題」がおおむね成り立って』いるということは、完全に理論的な経済モデルを前提とすると、財政政策の景気刺激としての効果が少ない(というかゼロ)ということではなかろうか。以前から日本では「リカードの中立命題」が良く該当しているとか、恒常所得仮説がよくあてはまっているという文献が記憶にあるので、これは事実だと思うが、そうであるならば日本の経済学者は今まさに行われようとしている「積極財政」に対する警鐘が必要ではなかろうか。
11/21
日経 OPINION 「分散周遊がひらく観光立国の未来」:オーバーツーリズム問題についてアイスランドの事例を紹介している。①周遊インフラの整備:つまり観光客を国内に分散させるためのインフラ整備②体験型アクティビティの圧倒的な質と量で価値を創出③デジタル化による省人化と統制 これらの検討は日本でも有益だろうと思う。