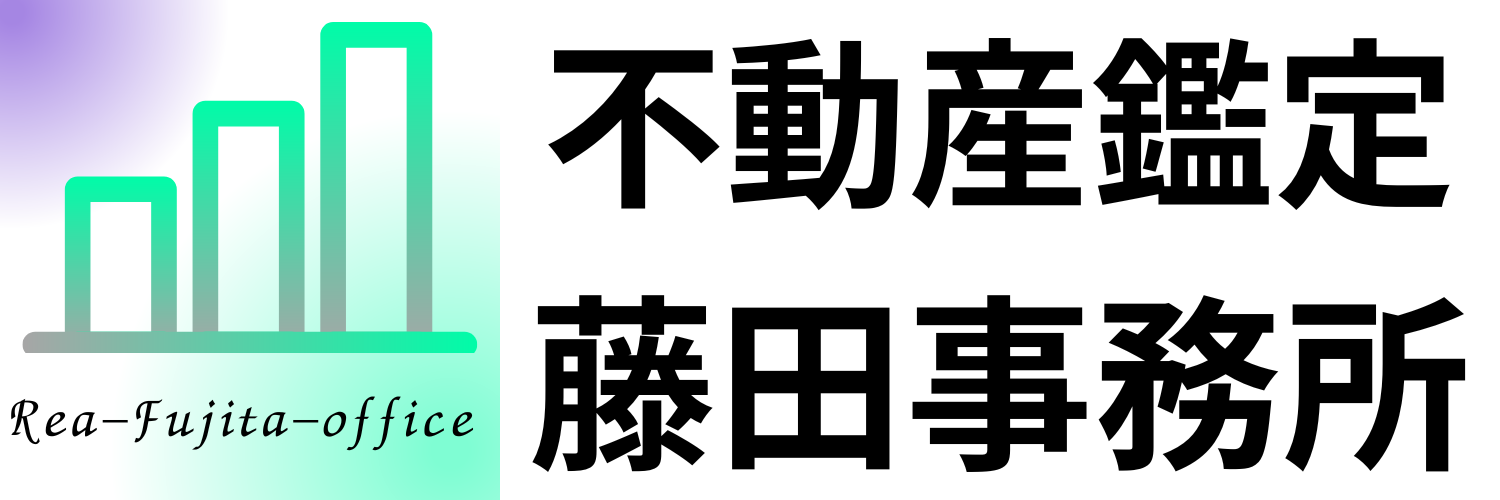春琴抄 谷崎潤一郎
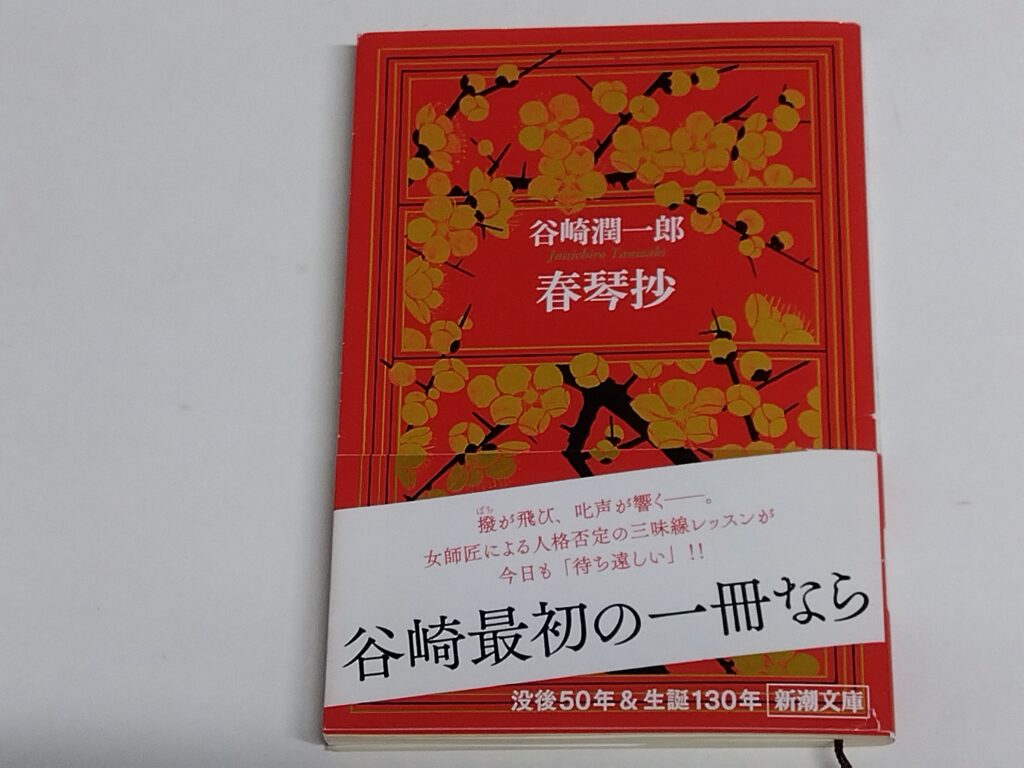
文庫本の帯に「谷崎最初の一冊なら」と書かれている。確かに新潮文庫では小説本文は100ページに満たない量であるし、春琴と佐助の純愛物語風で取組みやすそう、しかものちに続く谷崎先生の いわゆる「変態的物語」を考えると、最初としては適切だと思われます。
しかしまず、読み始めるとすごい違和感。なぜかと言うと無理やり句読点「。」が省かれている。つまり、2つか3つの文章が続いてしまってあるのでなれないと読みづらい。慣れてくると前の文章が頭に残ったまま次の文章の読みに入っていくので、頭に残りやすいかもしれない。ただこの手法をまねた小説はあまり見当たらないので、文章表現上効果的な方法とは思われていないんじゃないかな?逆パターンがあって、文章が異常に短いタイプの小説がある。今から20余年前にアメリカの作家ジェイムズ・エルロイがホワイトジャズという小説で始めた「クランチ文体」というもの。体言止めであったり、/(スラッシュ)で文章を無理やり終えたりという方法を使ったもの。これも初めは違和感がすごいのですが、慣れてくると独特のリズムが感情に響く気がすることもある。これはなかなかいい方法で、真似ていた作家が沢山いたと思う。確か岐阜県各務原市の出身である「冲方丁(うぶかたとう)」さんもこれをまねて書いた小説があったと思う。こちらは意味のあるものだった。
話は良家のお嬢様とこれに尽くす奉公人として始まりますが、奉公人の佐助に対し春琴が三味線を教え始めるところから、少しづつ怪しくなり始めます。谷崎先生は早い段階から「変態の物語である。」と白状していて新潮文庫だとP35に「稽古に事寄せて一種変態な性欲的快味を享楽」と書いている。谷崎先生の小説は、そのほとんどが「異常・変態」であって「春琴抄」は少々間接的な感じがありますが、それでもやはり「一種変態な性欲」を描こうとしているので「谷崎最初の一冊なら」というコピーも納得です。
ところで春琴抄には「日本文学史上最大のミステリー」と少々大げさに言われている部分があり、春琴が熱湯を浴びせられ顔に醜い跡が残る、というエピソードがある。この部分について犯人は誰かについて明確な言及がなく、普通に考えると春琴に三味線を習っていたぼんぼんなのですが、ひょっとして佐助?まさか春琴の自演?ということも成り立ちうるのです。この後の展開はぼんぼんが犯人であっても「一種変態な性欲的快味」なのですが、佐助説・自演説いずれであっても怖いくらいの「一種変態な性欲的快味」のイメージが増幅される感じで、ついつい様々な妄想にふけってしまう。春琴抄が世に出てから90余年が経過していますが、いったい何人の人が妄想にふけったか。ここだけでも名作の価値があると言える。