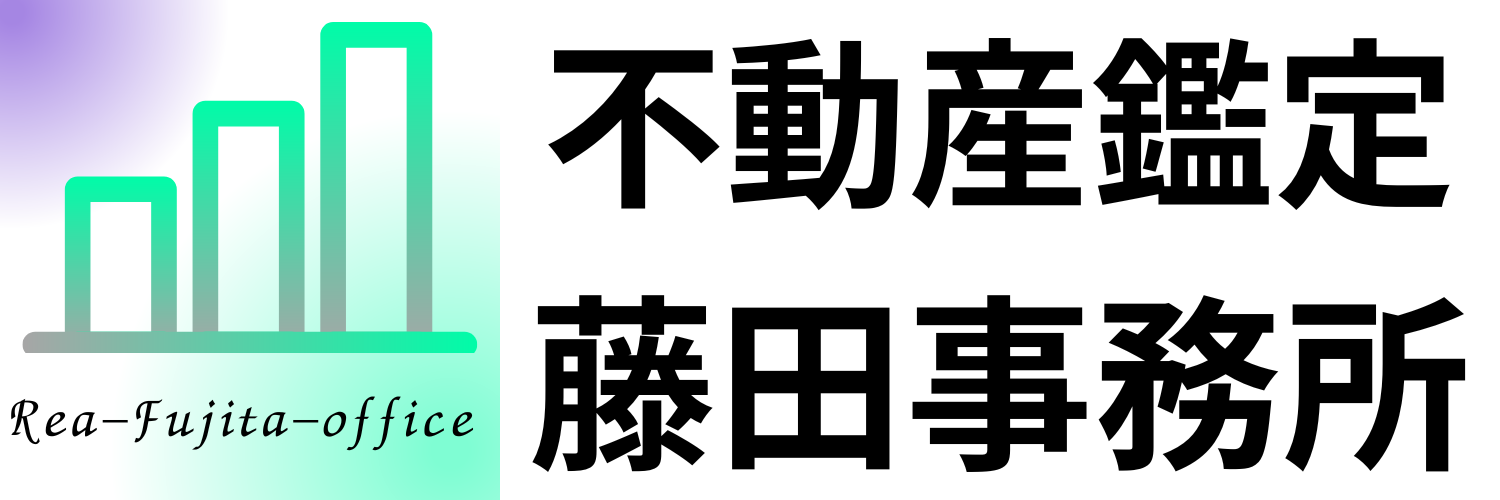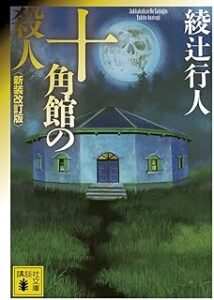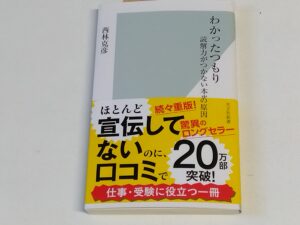殺戮に至る病(我孫子武丸)
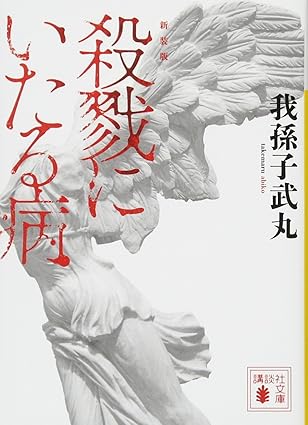
物騒なタイトルですが、内容をきちんと表現したタイトル、つまり相当に物騒な内容で、サイコパス・ホラーなどが苦手な方はおそらく最後まで読み切ることが難しい、そう言い切れるほど物騒な内容です。
ところが、この本も前回の「十角館の殺人」と同じく2度目を読まずにはいられない小説なのです。ラストページに近いところで真相が明らかになる。でもこの真相がこの本の真実であるなら、いったい自分が今まで読んできたのは何なのか!?ということで、そのあたりを確認しないわけにはいかず、もう一回読むことになる。
2回目を読んでいるところで、この殺人鬼の人でなし具合は、読者の注意をそらすためにあえて並外れた人でなしにしている可能性が高いな、と感じてしまう。それ以外の理由でここまで残酷にする必要がない。
「十角館の殺人」では、トリックを成立させるためあえて大事な部分を巧妙に避けていた感じがしましたが、この「殺戮に至る病」では気づかせないために結構ギリギリを攻めている。結論を知った2回目だと、うっかりするとこれはバラしてしまっていないだろうか、と逆に気になるが、どうもギリギリばらしていない。これを初見でバッチリ気づくのは不可能だろう。恐ろしい小説である。
ところで、話は全く変わりますが、R7.8.26(火)の日経新聞の経済教室に「給付は消費を押し上げない」というタイトルで一橋大学の砂川貴一教授が論考を掲示しておられました。そこでは「物価水準の財政理論」や「リカード=バローの中立命題」などを持ち出して、給付(=拡張的財政政策・藤田の加筆)が消費を押し上げない(=財政政策の効果が限定的である・藤田の加筆)ということを、何らかのデータの分析によって論証しておられました(何のデータかは明示されていませんでした)。私としては「中立命題」よりもM.フリードマン教授の「恒常所得仮説」の方がしっくりくるのですが、私のようなものが偉そうに主張しても大した意味はありませんし、結論は変わりませんのでこの件は流します。
こういったことは、経済学者はもっと大きな声で社会に発信すべきだと思う。なぜなら、先日の参議院選挙で数多くの政党が物価高対策の名目で大規模な「消費税減税」を主要政策として訴求していたのですが、大学でマクロ経済学を学んだ者の端くれとして、選挙時の人気取りのためとはいえ、非常に苦々しい思いで見ていました。確かに米などを中心として価格が上がっているので、消費税減税をすれば助かると考える人は多いと思うのですが、国家予算を使う場合は、その効果について十分に検証しないといけない。現在の経済状況を考えると大規模な拡張的財政政策はたいして経済を好転させなかろうし、物価をさらに引き上げるだろう。
そのあたりを何も触れないまま、困っている皆さんの味方ですよ!的に訴えている政党は私から見ると「カオナシ」に近いものです。砂川先生、大きな声を出しましょう。