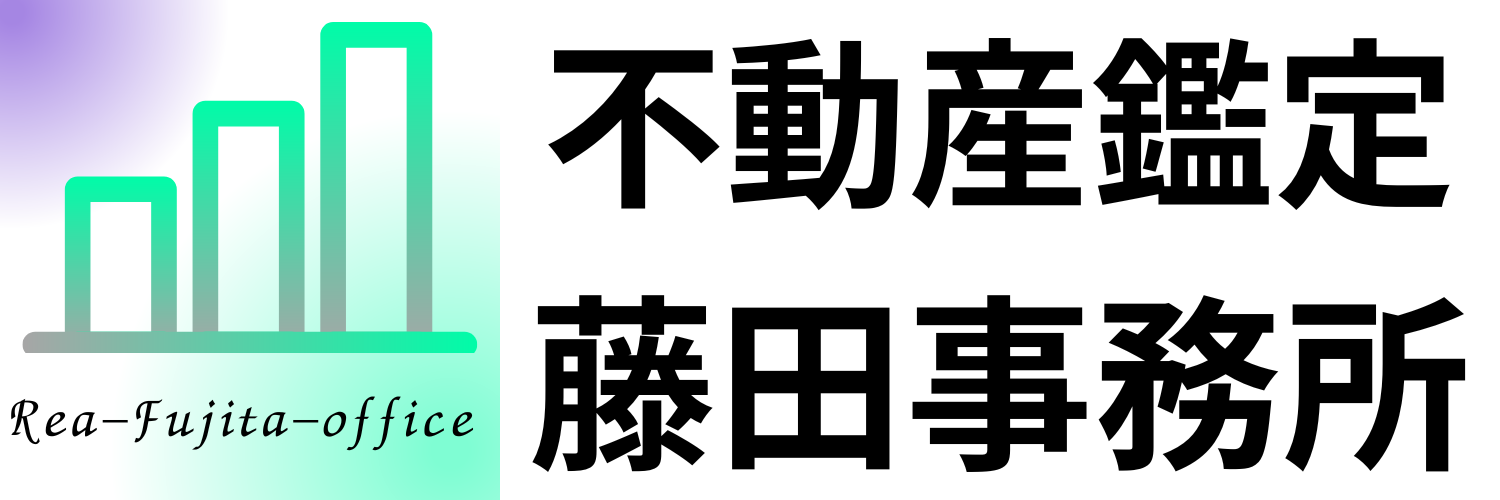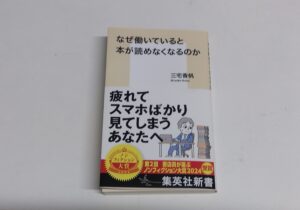鑑定評価書のご説明③「「Ⅲ.鑑定評価の基本的事項_1」

あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。.
今回は「鑑定評価書のご説明①」【鑑定評価書の構成 例】に記載した「Ⅲ.鑑定評価の基本的事項」について掲載します。
Ⅲ.鑑定評価の基本的事項
【記載例】
Ⅲ.鑑定評価の基本的事項
1.対象不動産の種別および類型
(1)種別
住宅地
(2)類型
更地
~~~~~~~~~~~~~~~記載例ここまで~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【ご説明】
「種別および類型」という不動産鑑定評価独特の言い回しですが、
- 種別は「不動産の用途による区分」で、具体的には「住宅地、商業地、工業地」といったものです。
- 類型は「不動産の利用形態及び権利関係による区分」で、具体的には土地の場合は「更地、建付地、借地権など」で、土地と建物の場合には「自用の建物およびその敷地、貸家およびその敷地、借地権付建物」などといったものです。
「不動産鑑定評価基準」では、この種別および類型を「不動産の経済価値を本質的に決定づける」としていて、少々大げさに聞こえるものの実はそのとおり大事なところで、だから鑑定評価書のかなり始めの段階に記載することになっているわけです。
そのココロは
(1)種別つまり不動産の用途によって、価値判断するときに見るべきポイントが変わるのです。具体的には
●「住宅地」では「住環境」や「生活利便性(つまり学校やスーパーなどが近いというようなこと)」に着目
●「商業地」では「商業の収益に影響を与える項目(つまり人通り、交通量が多いとか目立ちやすいとか)に着目
●「工業地」では「工業の収益、効率性に影響する項目(つまりICなどに近く原材料や製品の搬入出の効率が良いなど)」に着目
それぞれ、まず最も現実的な「用途」を判断したうえでそれぞれの不動産のどういったポイントに着目し価値判断していくかということが大切で、この判断がないと「この土地のここがいい、悪い」と言っても買う側の立場に立った議論にならず、言いたい放題の議論となって混乱してしまうわけです。
(2)類型は土地では「更地」なのか「建付地(建物が存在している土地で、土地だけを評価の対象にするのです)」によって価値判断が変わる、つまり「更地」では「買った方が自由なやり方で利用可能」一方「建付地」では「建物が存在しているため利用方法はおのずとその建物を前提としたものとなる」わけで、この「好きなように利用できるのか、存在している建物の制約を受けるのか」は価値判断として大変大きなポイントになるのです。
土地と建物の場合は「自用の建物およびその敷地」では、買った方の好む方法で利用できる、一方「貸家およびその敷地(いわゆる賃貸マンション又は賃貸ビルなどです)」では、入居者・店子がいるので買った方は自分が使うのではなく、毎月入ってくる賃料を目的にするわけです。この違いは評価方法そのものの根本的な違いにつながります。
こういった利用形態・権利関係を前提として価値判断をしないとこれも議論が混乱してしまうので、始めにきちんと明示するわけです。
~~~~~~~~~~~~~~~ご説明 ここまで~~~~~~~~~~~~~~~~
今回は「Ⅲ.鑑定評価の基本的事項」のうち「1.対象不動産の種別および類型」について語りました。このペースでいくと、鑑定評価書1冊分語るのにどれほどの時間がかかるか、という懸念が出てきますが、いろいろ省略して早く進めるのは本意ではありませんし、一回に情報を大量に投入しても、書くほうも読むほうも疲れてしまいますから、この感じで行くことにします。