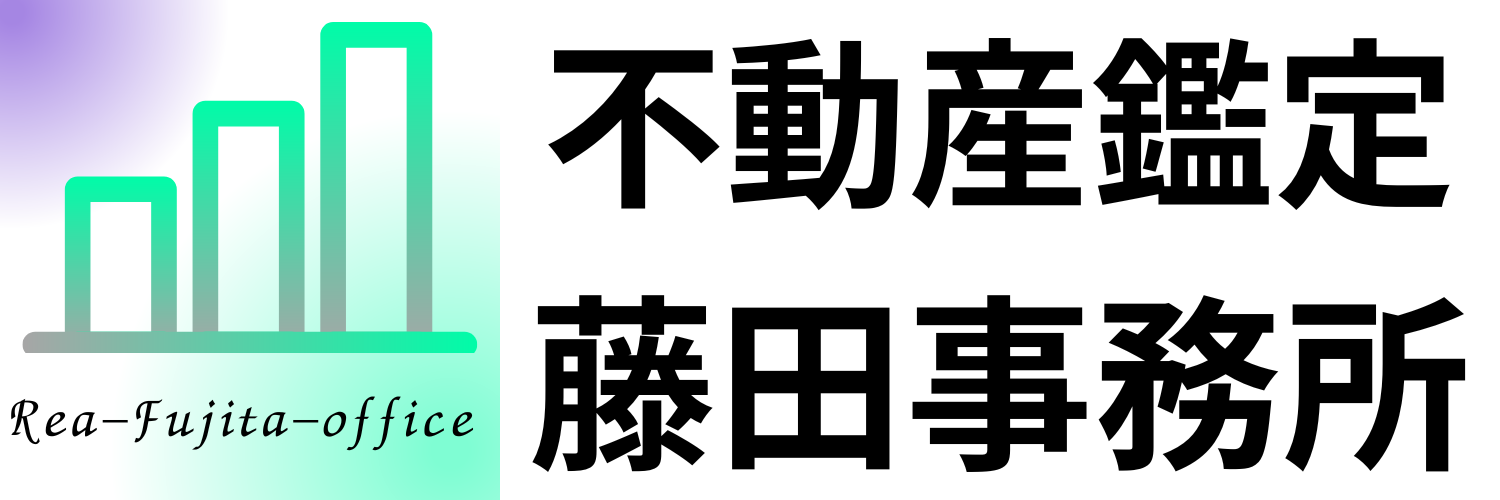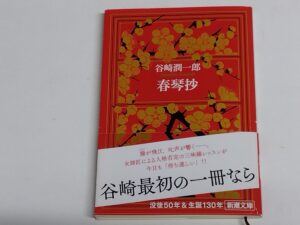鑑定評価書のご説明⑥ 鑑定評価の依頼目的等

今回は「鑑定評価書のご説明⑥」で「鑑定評価の依頼目的等」を記載します。
【記載例】
Ⅳ.鑑定評価の依頼目的等
1.依頼目的
売買の参考資料
グループ企業間による事業用不動産の売買における適正な価格の判断資料として。
2.依頼者以外の提出先等
依頼者以外の提出先:○○○○
依頼者以外への鑑定評価額の開示先:○○○○
鑑定評価額の公表の有無:無
後日、本鑑定評価書の依頼者以外の提出先若しくは開示先が広がる場合、又は公表する場合には、当該提出若しくは開示又は公表の前に当社あて文書を交付して当社及び本鑑定評価の担当不動産鑑定士の承諾を得る必要がある
~~~~~~~~~~~~~~~~記載例ここまで~~~~~~~~~~~~~~~~
【ご説明】
「1.依頼目的」について
「価格等調査ガイドライン運用上の留意事項」という法令等に準じた不動産鑑定評価の内容を規制している文書があり、そこで「利用者の判断に大きな影響を与えると判断されるばあいについて」※1として、法令等により鑑定評価基準に則った鑑定評価が義務付けられている場合や、「公表される第三者・提出先に大きな影響を与えると判断される場合」※2などが例示されており、つまりこれらのように利用者の判断を誤らせる可能性が大きい場合等には、鑑定評価に則らない価格等調査で対応してはいけない又は安易に鑑定評価の条件を設定してはいけないということになっていて、その判断を的確に行うため鑑定評価の目的を単に「売買」「担保評価」「資産評価」など形式的な依頼目的だけでなく、依頼の背景等を可能な限り詳細に把握し、慎重に判断することとされています。
※1 法令等により鑑定評価基準に則った鑑定評価が義務付けられている場合とは、J-Reit等の運用資産の評価とか会社法の現物出資の価格証明であるとか、は法令等で鑑定評価基準に従った鑑定評価が要求されています。
※2 公表される第三者・提出先に大きな影響を与えると判断される場合とは、倒産法制における否認要件、担保評価、関連会社取引に係る土地・設備等の適正価格の証明としての評価などがあげられます。これらは、鑑定評価基準に則った鑑定評価が義務付けられるわけではないのですが、利用者の判断を誤らせる可能性がないかを慎重に検討することが要請されます。
「2.依頼者以外の提出先等」について
「1.依頼目的」についてのところで記載した、「鑑定評価書の利用者の判断を誤らないようにする」という目的のため、鑑定評価書及びその内容の影響が及ぶ関連者の範囲を明確にしておくことが要請されるのです。J-Reitや上場企業の会計に関連した鑑定評価では、判断に影響を与える範囲が、一般的な投資家全般となっていくので、かなり慎重な判断が要請されるわけです。