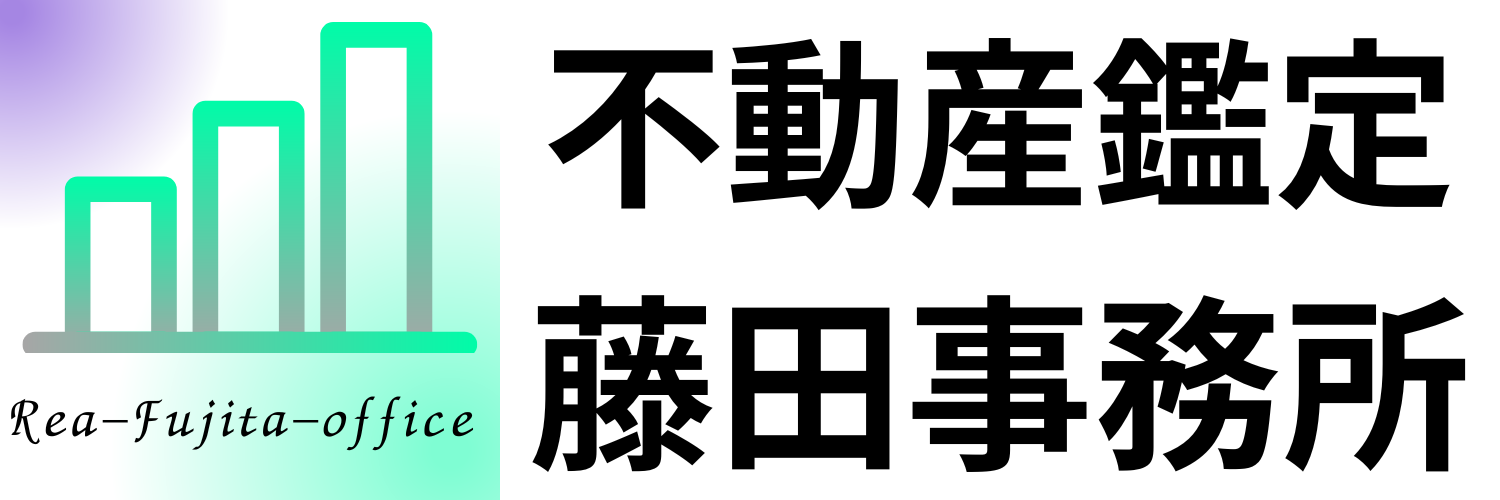なぜ働いていると本が読めなくなるのか
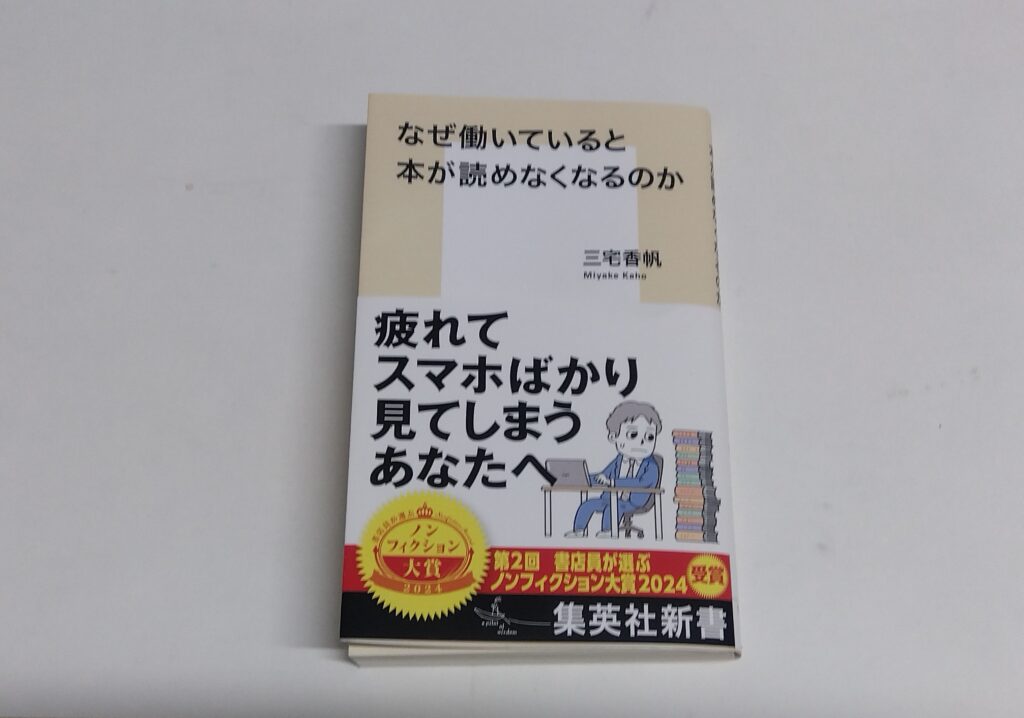
私の数少ない趣味が読書なのですが、最近(正確にはもう5~6年になるのですが)読書量がめっきり減りました。具体的にはピークでは年間100~150冊程度は読んでいたのですが、最近は年間20~30冊程度まで落ち込んでいます。そんな中、集英社新書「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」という本が目にとまりました。「年間100~150冊読んでいた時も仕事はしていたのだから、この本の趣旨とは少し違うのではないか。」「そもそも、なぜ読書量が減っているのか、自分で分かっているだろ。」という自問はあったものの、それを理由に読むのをやめては「理由を作って逃げたな。」という自己嫌悪が大きくなるだろうと思われ、読んでみることにしました。
読書量が減った原因は、新聞だろうと自分で分析しています。ちょうど読書量が減ったタイミングで①中日新聞はほぼすべて読む。②日経は、通常の記事に加え「社説」「5または6ページくらいに載っているいわゆる”オピニオン”の記事」「経済教室」をなるべく全部読む。③(これは最近半年くらいなのですが)「岐阜新聞」「中日スポーツ」もなるべく読む。そうは言っても③まで購入しているとなかなか厳しいので、会社の近くに③が置いてあるランチのお店を3つほど見つけまして、お昼にサクっと目を通す感じにしています。なぜそんなことをするのか?といいますとa.日経を駅の売店で買うようにしたら、生まれついての貧乏性が発揮されて「1部200円も出しているのだから、きちんと読まないともったいない。」と思うようになり、上記の②をやるようになりこれが習慣化したわけです。そうしますと、特に日経は朝だけではとても読み終わらないので、上記②を帰宅途上から初めて「できれば夕食前に終える。でも夕食後まで持ち越すこともある。」ということがルーティーンになり、結果として、読書への気力がなくなってしまう訳です。これはこれで意味のあることだと思われるし、それなりに楽しいのでやめるつもりはないのですが、そうは言っても読書量の減少はかなり寂しく、どうにかならないものかと思っていた訳です。
本書は①「どうして労働と読書が両立しづらいのか。」ということが、明治以降の労働と読書の歴史的経緯に照らして論じられており、②最終的には「どうすればよいのか。」というところまで踏み込まれていました。ただし、どちらかというと②の方は付け足しで、①の論述が主力となっていました。最終的には、人生観というか仕事観のような感じでまとめられていまして、あまり詳細を記述してしまうと問題があろうと思うのでこのくらいにしますが、かなり「なるほど」感の強い本です。
私としては、新聞に読書パワーが奪われている、という自己分析があったわけですが、よく考えてみるとスマホを眺めたり、くだらないテレビ番組を意味なく眺めたりという時間が結構あることに気づきまして、ここをクリアにできればそれなりに解決するのではなかろうか、という気持ちになりました。
自分の読書量が少ないと思っているすべての読書家に強く推奨できる本です。