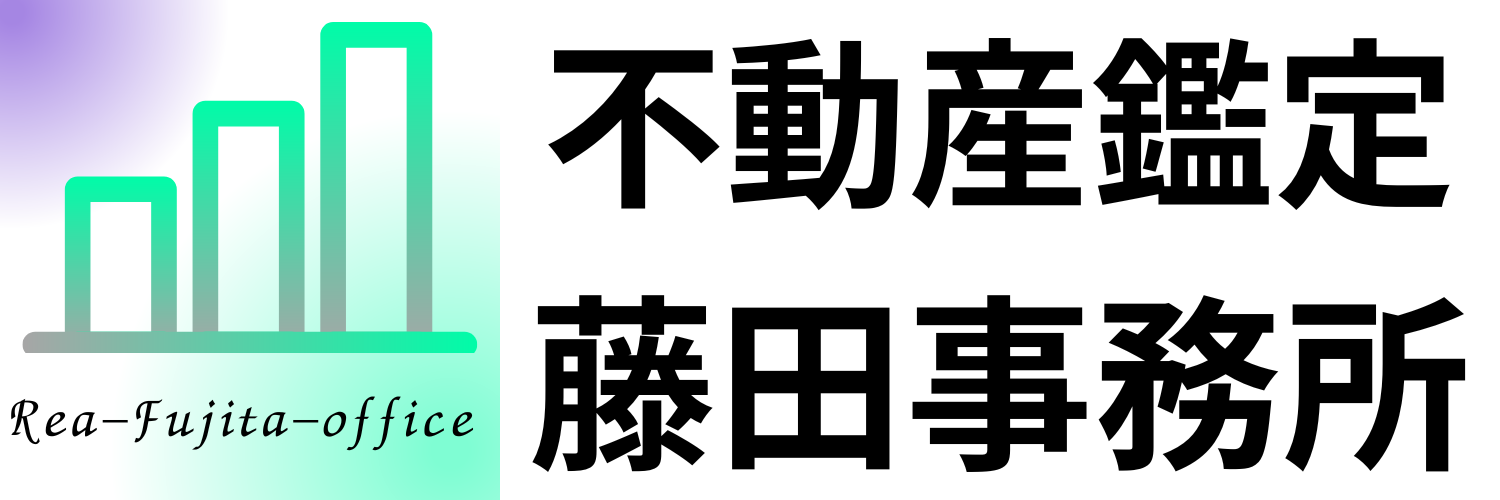輪中館・輪中生活館(大垣市入方)

輪中館(公民館のような施設の2階にあります)
輪中館は大垣市入方というところにあります。第1感で「あれ、輪中ってもう少し南の海津町周辺のことじゃなかったかしら。」と思ったのですがこれが私の見識の低さでした。輪中とは「一般的には堤防で囲まれた構造、あるいはその集落を意味する。濃尾平野の木曽三川(木曽川・長良川・揖斐川)とその支流域にあたる岐阜県・三重県・愛知県の県境付近に発展しており」(Wikipedia -輪中- から引用)となっており、思っていたよりずっと広い範囲で、濃尾平野の木曽三川(木曽川・長良川・揖斐川)は今のように3つの川としてきれいに流れているのは最近のことで、以前はそれぞれが入り乱れて流れており、それらが氾濫を繰り返しそのあたり一帯が輪中であった訳です。
輪中館の中ではその歴史や風俗、功績のあった人物などの説明があって私としては「輪中の地理的位置」をはじめとして大変興味深い情報を知ることができました。これがなんと入館料無料!これをご覧のみなさまにはご訪問を強くご推奨します。ところで右側写真の船。なんだこれは、とつい写真を撮ってしまったのですが、周辺にご説明を見つけることができず、??と思っていたらそののちに判明することとなったのです。
輪中館の見学を終了したところで、係員の方が「近くに輪中生活館というものもあって、今日は閉館ですがもしよろしければ開けますので見ませんか。」と望外のお誘いを受け、ムムッお昼が近いけどな、と思いつつせっかくなのでお願いしました。こちらは大垣市の重要有形民俗文化財に指定されている「名和」さんという方の輪中民家でした。開けていただいた入り口を入ると土間になっており、天井に先ほど見かけたような船がつるしてありました。これは「上げ船」といって洪水時におろして避難したり、荷物を運んだりするために使う船だということです。
私としては、家の構造が「ふすまを外すと8畳の間×4のような大きな部屋になりお葬式が自宅で行える」ようになっており、葬式でなくても盆や正月などに親戚が集合し、大きな部屋に布団を並べて寝るなどが可能な構造となっており、これは懐かしいものだ、と係員さんとコミュニケーションが取れて、大変楽しい時を過ごしました。
ところで、木曽三川が頻繁に氾濫しその度に生命の危険を脅かされなければならないところにしがみつくようにして暮らしているのはなぜだろう、と思い心優しき係員の方にお聞きしてみると、どうもこのエリアの農業生産性が高く単位面積当たりの取れ高がほかの地域を圧倒しているようで、つまり古代メソポタミア文明のチグリス・ユーフラテス川のような役割すなわち氾濫のたびに栄養豊かな土壌を運び込んでくるということになっているようでした。なるほど。
西濃地区に由来の方には是非とも訪れていただきたい施設です。この施設がなんと無料。しかも大垣市は比較的外食が充実しているので、半日程度のレジャーに最適。