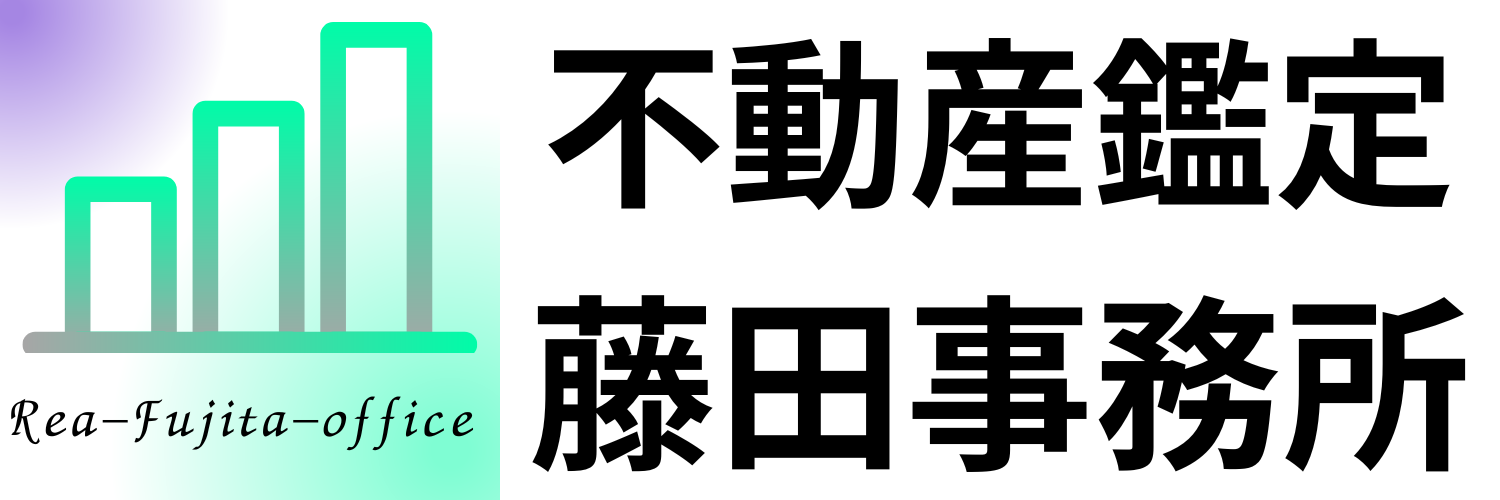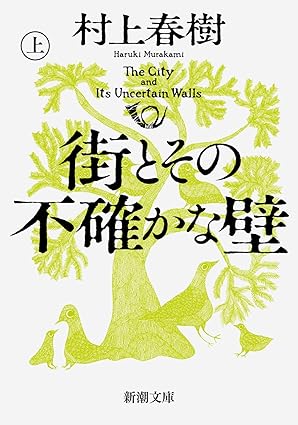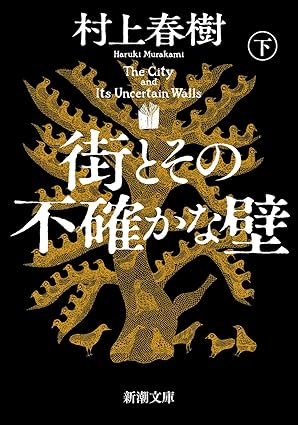街とその不確かな壁(村上 春樹)
日本を代表するべストセラー作家、村上 春樹。「ノルウェイの森」だけで1,000万部を超えていて、それ以外に100万部を超えている小説が10以上あるという大作家。ここまでくると好きかどうかは別として、小心者の私としては読まないでおく度胸がない、という存在。
好きな小説家かと言えば、必ずしもNo.1ではない。でも読んでいる最中はかなり夢中になって読んでいる。それでも、ちょっとスカした感じは好きではない。翻訳もかなりの部数を発行していますが、これらを読むとスカした感じは村上先生のオリジナルではなく、一定程度のグループを形成している作風なのだとわかります。
レイモンド・チャンドラーという作家がいて、確かこの方の「ロング・グッドバイ」という小説が村上先生の最初の翻訳ものだったと思う。これを読んだ時「スカした文体は村上先生のオリジナルではなかったのだな。」ということが解った。でももともと「長いお別れ」というタイトルだったものを「ロング・グッドバイ」にするところはスカした感じの自己顕示欲かな、とも思う。
「スカした文体」とか「好きではない」とケチをつける位なら読まなければよい。その通りなのですが、村上先生くらいまで行くと、無視できない。つまり、もしノーベル賞に・・・ということになった時に「読んだことがないのです」というのは、読書好きとしては避けたい。受賞して人気が出てから読み始めて「にわか」みたいになるのは格好悪いし。それに読んでみると、案外夢中になって読んでいる。そんなこんなで、村上先生の長編小説はほとんど読んでいますし、翻訳ものもかなり読みました。こういった場合に素直に好きだと言える人間になれたら良いのに。
それで「街とその不確かな壁」。村上先生が得意な「パラレルワールド」もの。青春期に付き合っていた彼女が想像の中で作り上げた壁の中にある別世界。ここに行ったり戻ったりする。つまりこれは何かの「例え」で、これをどう解釈するかは読者によって自由なわけです。でも、ここでカズオ・イシグロ先生の作風が思い出される。カズオ流も「信頼できない語り手」が本当のことをストレートに表現しないで、そのうえで「どうしてストレートに表現しない、又はできないのか。」というところから本心を解釈していく。この場合村上流だと全くのファンタジーを用いて場面を仕立てるのですが、イシグロ流だとリアリティある舞台が前提になっている。そうすると「わざわざファンタジーを持ち出すってどうなのかな?」と思ってしまう。ケチをつけながらも、喜んで読んでいる訳ですからいいのですが。
以上