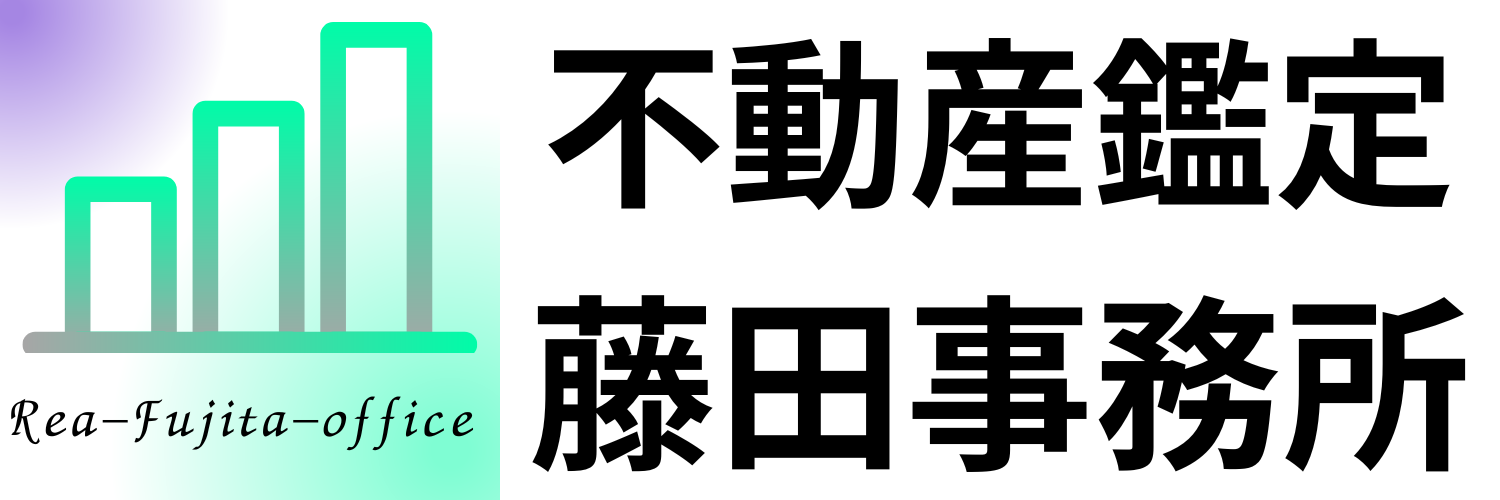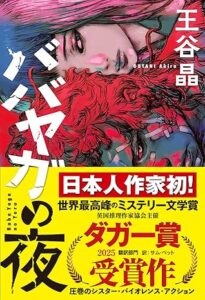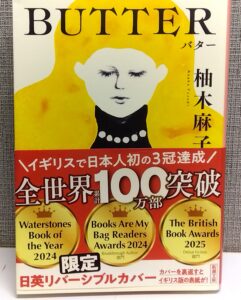日経新聞(10/13~/19)

日本経済新聞の記事で、心に残ったもののまとめ(藤田の作成した「概要」)と意見(もちろん私の考えですから、気に入らないものは笑い飛ばしてください)を時々記載します。
経済教室で3日連続で「日本型経営に必要なもの」という特集が行われました。「中」だけがすんなりと頭に入りませんでしたが、「上」「下」は示唆に富むものでした。
高市早苗氏の総理氏名が濃厚になったそうですが、拡張的金融政策・拡張的財政政策、物価高対策、日銀の金利政策に対する意見を聞いているときちんとした整理がされていないように思う。経済政策は総理が考え出してやるものではなかろうから、良さそうなものですが、なんらかの指示を出すであろうから、きちんと整理しておいていただきたい。
10/15 経済教室 「日本型経営に必要なもの 上:本庄裕司 中央大学教授)
まとめ
日本型雇用システム(新卒一括採用・終身雇用)は雇用の安定に一定の役割を果たしてきた一方、人材の流動性低下につながり結果としてスタートアップ企業の誕生と成長を停滞させてきた側面は否めない。多くの人材がリスクをとって挑戦できるようセーフティーネット等の制作の検討、未上場株式市場の整備や資金供給の制度設計が必要である。スタートアップ企業が既存企業との競争を通じ日本経済に活力を与える事を期待したい。
意見
スタートアップ企業の活力の少なさが日本経済の停滞の一因である可能性は大きい。
10/15大機小機
まとめ
自民党新総裁に選ばれた高市早苗氏は安倍路線の嫡流である。アベノミクスの第一の矢はリフレ政策であったが2%の物価上昇目標の達成は困難であった。高市氏は「デフレで無くなったと安心するのは早い」「金利を今あげるのはアホやと思う」などの発言がある。日本経済を政府が金を使うことで先導することはできない。
意見
●拡張的金融政策・拡張的財政政策と物価高対策は共存できない。今物価高対策を主張しているのは間違いなく人気取りを目的としたものである。
10/17 経済教室 「日本型経営に必要なもの 中:松田千恵子 東京都立大学教授)
まとめ
日本企業の深刻な人材問題は経営者の側にある。日本企業で経営者における最も重要な体験として挙げられるのが「修羅場体験」であるが、これは人事異動による偶然にゆだねられたものだ。経営について真剣に考え育成する仕組みを抜本的に設計しなおすことが急務である。
意見
●高度な企業経営にここに書いてあることが必要なのであろうがそればかりでもなかろうと思う。そういった事との比較検証まではこのスペースでは無理だろうが、理論で学べることで高度な経営ができるのなら学者に経営を任せれば日本の経済的地位向上になるのだろうか、という重要な疑問が解決していない。
10/17 経済教室 「日本型経営に必要なもの 下:山田仁一朗 京都大学教授)
まとめ
企業の動力は情熱だ。しかし末端までこれが伝わらない悩みを経営者は抱える。これは現代企業が「3つの異なる力」に引き裂かれそうになっているからである。その3つは「共同体の力」「市場の力」「国家と地球の力」である。これら3力の矛盾の解決の一つが経営陣と取締役会を異なる機能でとらえなおすことである。経営陣は実行→学び・痛み→次のサイクルに反映つまり「自己統治」を行う。取締役会は規律上の監視を行う。挑戦と学びが配分を動かし続け、情熱が制度と習慣に血肉化する、自己統治の循環が企業の生命線だ。
意見
●情熱という抽象的な言葉を持ち込んだことで、むしろこの方が先の「日本型経営に必要なもの 中」より具体性が増し、説得力を感じる。
10/17 国際面1 「プーチン氏を謝罪させた小国」
まとめ
ロシアのプーチン大統領はアゼルバイジャンのアリエフ大統領の会談で2024年12月のアゼルバイジャン旅客機の墜落がロシアの問題であるとして謝罪した。アリエフ氏は巧みにプーチン氏を自らの非を認めざるを得ない立場に追い詰めた。核大国の独裁者に対し善意や良心に訴えるのは無意味であり、超大国(米国)をバックにした力しか効果が見込めない。大統領在任22年で外交経験が豊富なアリエフ氏がこの国際政治の冷厳な現実を熟知していたのは間違いない。
意見
ウクライナもどうにかならないものだろうか。
以上